
ヘルベルト・ブロムシュテット指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
(録音:2019年10月 ライプツィヒ、ゲヴァントハウス(ライヴ録音))
現役最高齢、当時92歳のブロムシュテット(1927~)が、1998年から2005年にかけてカペルマイスター(首席指揮者)を務め、その後名誉指揮者となっているライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団とライヴで録音した交響曲全集の1枚。
90歳を超えているとは思えない瑞々しい演奏。細かいところまで彫り深く表現されながら、音楽は停滞することなく進んでいくバランスも巧みです。これまで聴いた演奏ではあまり意識していなかったパートの動きが効果的に聞こえるところもありました。個人的にはもう少し前に進む推進力を感じさせる演奏の方が好みですが、オーケストラの響きの美しさも見事で、優れた演奏だと思いました。
手元にある交響曲第2番の他のCDも聴いてみました。録音が古い順に紹介します。

エデュアルト・ファン・ベイヌム指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
(録音:1954年5月17-19日[第2番]、1956年9月24,25日[第3番]、1958年5月1-3日[第4番]、1958年10月6,7日[第1番] アムステルダム、コンセルトヘボウ)
ベイヌム(1901~1959)が、1945年から亡くなるまで首席指揮者を務めたアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団と、モノラル末期からステレオ初期にかけて録音したブラームス交響曲全集で、録音された順に、第2番・第3番はモノラル、第4番・第1番がステレオになっています。
最も早く録音されたこの第2番は、モノラル、ダイナミックレンジの狭さなど、録音の古さは否定できませんが、リマスターもあって、音自体は聞きやすい感じになっています。早めのテンポ、実直、端正な解釈で、若々しい推進力を感じさせる演奏です。ベイヌムは57歳で急逝してしまいましたが、もっと評価されていい指揮者だと思います。せめて録音技術が向上した1960年代まで活躍して、もっと録音を残してくれていれば・・・と思わずにはいられません。

ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団
(録音:1967年1月6日[Op.73]、1964年10月16,17日[Op.90] クリーヴランド、セヴェランス・ホール)
セル(1897~1970)が1946年から亡くなるまで音楽監督を務めたクリーヴランド管弦楽団と1964年から1967年にかけて録音したブラームス交響曲全集の一枚。
セルの晩年、クリーヴランド管弦楽団とのコンビの絶頂期といえる時期の録音、その中でも、この第2番は最後に録音されています。このコンビの録音は、特に早い時期のものはデッドな雰囲気のものも多いのですが、本盤では、温かさも感じる音になっており、より聞きやすくなっています。
セルの演奏は、厳格で折り目正しい、というのが一般的な評価だろうと思います。曲によっては、その特色が裏目?に出て、音楽が停滞しがちで前に進まない演奏もあるのですが、この演奏は、そうした印象は薄く、透明感のある響きで、細部までコントロールされ、立体的で格調の高さを感じさせる演奏になっています。

カレル・アンチェル指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団、ヨゼフ・スーク[Vn]、アンドレ・ナヴァラ[Vc]
(録音:1963年9月30日,10月1日[Op.102]、1967年6月5,7日[Op.73] プラハ、ルドルフィヌム)
アンチェル(1908~1973)が当時常任指揮者を務めていたチェコ・フィルと録音した1枚。ブラームスの交響曲では、このほかに第1番の録音も残されています。アンチェルは、1950年からチェコ・フィルの常任指揮者を務めていましたが、1968年に起こったチェコスロバキアの変革運動「プラハの春」により同年8月にソビエト連邦軍主導のワルシャワ条約機構軍による軍事介入が起こった際、単身アメリカに演奏旅行中だったため、帰国を断念してカナダに亡命し、1973年に亡くなっていますので、1967年のこの録音は、アンチェルとチェコ・フィルのコンビとしては、最後期の録音ということになります。
明るく開放的な響きで、過剰な感情移入なく直截的なきびきびとした表現を主体としながらも、情感も漂わせ、造形のしっかりした優れた演奏。ホルンやトランペット、クラリネットのビブラートなど、この当時のチェコ・フィルのローカルな特色を感じさせる響きは、ドイツ・オーストリア系のオーケストラでは見られないもので、好き嫌いあるかもしれませんが、個人的には味を感じます。

カール・ベーム指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、クリスタ・ルートヴィヒ[A・Op.53]、ウィーン楽友協会合唱団[Op.53]
(録音:1975年5月[Op.73]、1976年6月[Op.53]、1977年2月[Op.81] ウィーン、ムジークフェラインザール)
ベーム(1894~1981)が1970年に名誉指揮者の称号を与えられたウィーン・フィルと1975年の5・6月に一気にスタジオ録音した交響曲全集からの一枚。カップリングの2曲は、交響曲全集の完成後、1976年から1977年にかけて録音されています。
格調の高さを感じさせる演奏。全体的にゆったりめのテンポで、基本的にはインテンポの中で音楽が展開していきますが、自然体でよどみなく音楽が流れ、落ち着いた呼吸の中で自発的なアンサンブルが息づいている印象。派手さ、華やかさはありませんが、何とも滋味深い演奏です。重厚感はありませんが、1970年代のウィーン・フィルの美しい響きを良く捉えた録音もいい感じです。

エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団
(録音:1978年4月29日[ウェーバー・ブラームス]、4月30日[シューベルト] レニングラード、フィルハーモニック大ホール(ライヴ録音))
ムラヴィンスキー(1903~1988)のブラームスの交響曲は、全ての曲で、1938年から亡くなるまで常任指揮者を務めたレニングラード・フィルとのライヴ録音が残されていますが、その中では第2番を最もよく取り上げていたようで、この本拠地レニングラードでのライヴ録音のほかに、同年の6月に演奏旅行中のウィーンで行った演奏会のライヴ録音もリリースされていますし、その前年の日本への演奏旅行時にも演奏されており、その際の放送用録音もCD化されています。
厳しさと寂寥感が漂い、鋭い透徹したまなざしを感じさせる演奏。独特のスコアの読みで、いわゆるドイツものの王道の演奏を期待する人には向きませんが、個性的ながら魅力ある演奏で、ムラヴィンスキーが好きな方は一度聴いてほしい演奏です。なお、同じコンビのチャイコフスキーやショスタコーヴィチの録音のように、ロシアっぽい音感にあふれた演奏だろうと思いきや、金管楽器の強奏は控えめで、響きの違和感はあまり感じさせず、意外に普通に聴けます。

レナード・バーンスタイン指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
(録音:1982年9月 ウィーン、ムジークフェラインザール(ライヴ録音))
バーンスタイン(1918~1990)が、1981年から1982年にかけてウィーン・フィルとライヴで録音した交響曲全集からの1枚。
バーンスタインの1980年代に入ってからの演奏は、特に緩徐楽章などでテンポが目立って遅めになった印象があります。この演奏もその例に漏れず、比較的ゆっくりめのテンポで、オーケストラを十分に歌わせ、音楽の振れ幅も大きいダイナミックな演奏。今回紹介した演奏の中では、最も濃厚でロマンティズム漂う演奏といえます。やや腰が重めな感じもあり、私の好みとはちょっと違いますが、ウィーン・フィルの美しい音が存分に味わえる演奏になっています。
これらのCDの楽章ごとの演奏時間を比較してみると、次のようになります。(第1楽章の○×は、提示部のリピートの有無です。)
- ブロムシュテット Ⅰ21'04"○/Ⅱ09'37"/Ⅲ5'04"/Ⅳ09'06"
- ベイヌム Ⅰ13'26"×/Ⅱ09'17"/Ⅲ4'58"/Ⅳ08'44"
- セル Ⅰ15'37"×/Ⅱ09'08"/Ⅲ5'42"/Ⅳ09'20"
- アンチェル Ⅰ14'59"×/Ⅱ09’16"/Ⅲ5'15"/Ⅳ09'00"
- ベーム Ⅰ15'34"×/Ⅱ11'40"/Ⅲ5'37"/Ⅳ09'54"
- ムラヴィンスキー Ⅰ15'26"×/Ⅱ09'09"/Ⅲ5'00"/Ⅳ09'12"
- バーンスタイン Ⅰ20'40"○/Ⅱ11'58"/Ⅲ5'32"/Ⅳ10'05"
第1楽章はリピートの有無もあるので単純に比較できませんが、第2楽章を除いて、いずれもベイヌム盤が最も演奏時間が短くなっています。ブロムシュテット盤も、第1楽章こそ、リピートもあって最も長くなっていますが、そのほかの3楽章は、中庸、あるいはむしろ相対的には速めの部類に入っていることがわかります。90代という高齢を感じさせないのは、こうしたところにも表れていると思います。
なお、手元にはないのですが、この曲の演奏でとても印象に残っているのは、カルロス・クライバーが1991年にウィーン・フィルを振ったライヴ。CDではなく、DVDとして発売されていました。これは名演です。
![ブラームス : 交響曲第2番&大学祝典序曲 / ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団&ベルベルト・ブロムシュテット (Brahms : Symphony No.2 & Academic Festival Overture / Gewandhausorchester Leipzig & Herbert Blomstedt) [CD] [Import] [Live] ブラームス : 交響曲第2番&大学祝典序曲 / ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団&ベルベルト・ブロムシュテット (Brahms : Symphony No.2 & Academic Festival Overture / Gewandhausorchester Leipzig & Herbert Blomstedt) [CD] [Import] [Live]](https://m.media-amazon.com/images/I/619bcKJ1JzL._SL500_.jpg)
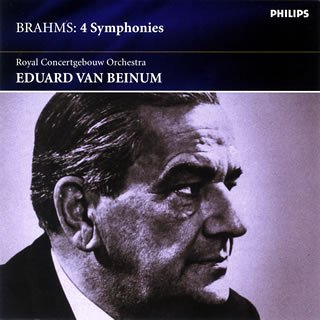



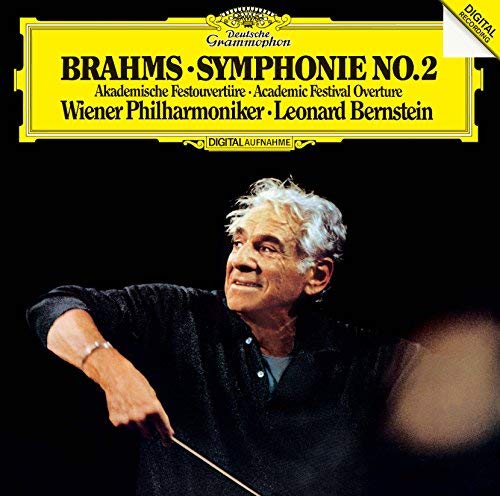
![モーツァルト 交響曲 第36番 / ブラームス 交響曲 第2番 [DVD] モーツァルト 交響曲 第36番 / ブラームス 交響曲 第2番 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/21M8C7E8CWL._SL500_.jpg)